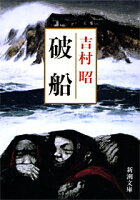ご覧いただきありがとうございます。
本と宴へようこそ。

どうも、宴です。
船は難破すると一大事ですよね。ところがなんてことでしょう。難破船を待ちわびている人たちがいたのです。彼らはそうしないと生きていけない定めにあったのです。
ということで、今回は吉村昭さんの『破船』をご紹介させていただきます。
<おすすめ記事>
破船/吉村昭
二冬続きの船の訪れに、村じゅうが沸いた。しかし、積荷はほとんどなく、中の者たちはすべて死に絶えていた。骸が着けていた揃いの赤い服を分配後まもなく、村を恐ろしい出来事が襲う……。嵐の夜、浜で火を焚き、近づく船を坐礁させ、その積荷を奪い取る――僻地の貧しい漁村に伝わる、サバイバルのための異様な風習“お船様"が招いた、悪夢のような災厄を描く、異色の長編小説。(Amazon紹介ページより)
| 異様 | 10/10点 |
|---|---|
| ドキドキ | 8/10点 |
| 感動 | 9/10点 |
| 切なさ | 10/10点 |
| 読みやすさ | 8/10点 |
| 総評 | 10/10点 |
書評・感想文

孤立した村
怖い小説を読んでしまいました。ホラーではありません。これは昔々のお話です。ひょっとするとこういう類の出来事は、いたる所で行われていたのかもしれません…
本作『破船』はとある海に囲まれ、孤立した村の物語です。村の独自の考え方や生き方。そして、お船様という決して村の外には漏れてはいけない秘密。現代から見ると狂気に満ちた村の生活を吉村昭さんは、実際にあったかのようなリアルな筆致で描き出します。
村の掟
まず読み手は村の貧困に同情し、そのしんどさに共感を抱くことでしょう。それぐらい村は貧しかったのです。
そして、昔ながらの村に縛られた人々に憐れみを覚えることでしょう。村長の言うことは絶対であるし、村の掟からも離れられない。今よりも生きる選択肢がなかった時代の辛さが窺えます。
ところがです。お船様の存在が村の狂気とも言えるものを露わにしていきます。何だかゾワゾワもしてきますが、村の人々はただ村のことを考え、生きようとしていただけでした。正常は狂気の一種と言いますが、村の人にとってはこれが正常だったのです。
必死に生きた結果
そんな正常の中で生きる主人公には胸を打たれてしまいます。この村は決して良い村とは言えませんが、その村の中で必死に生きた結果が涙を誘います。
孤立した集団の中で生きていく狂気と想い。それらを孕んだ痛いほどに突いてくる戦慄は、読み手の心を大きく揺らし、同時に熱くすることでしょう。
村の生き様を、ぜひ目に焼きつけてください。
心に残った言葉・名言
死は霊帰りまでの深い休息期間であり、村人たちが長時間悲しむことは死者の安息をかき乱すものだとされている。

「情などかけてはならぬのだ。かれらを一人でも生かしておけば、災いが村にふりかかる。打ち殺すことはご先祖様がおきめになったことで、それが今でもつづけられている。村のしきたりは、守らねばならぬ」

もがさは流行り病で、熱に苦しみ、顔や手足に吹出物ができたあげく、狂い死にする者もいる。たとえ死をまぬがれたとしても、吹出物の痕が醜いあばたとして顔や体中に残る。

吉村昭さんの他作品
最後に

村のしきたりに縛られていた人、自分の村はお船様やってましたという人、やりきれない切なさを味わいたい人にはおすすめなので、ぜひ読んでみてね。
それでは本日はこのへんで。
ご覧いただきありがとうございました。